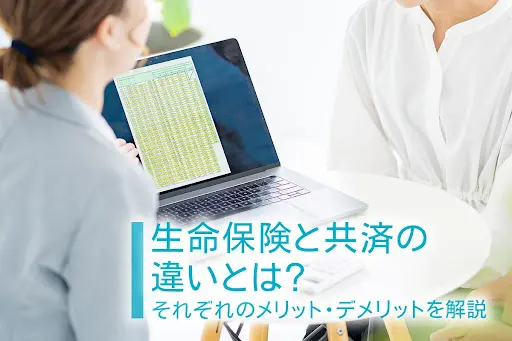生命保険と共済は、どちらも不測の事態が起こったときに現金を給付する事業である点が共通していますが、詳細な点は異なります。
加入を検討する際は、生命保険と共済の違いを理解したうえで、ご自身に合ったものを考えることが大切です。
本記事では、生命保険と共済の違いやそれぞれのメリットとデメリットなどをわかりやすく解説します。
生命保険と共済の違い

生命保険と共済は、どちらも「相互扶助」の精神にもとづいて運営されています。相互扶助とは、多くの人が少しずつお金を出し合ってひとつの共有財産をつくり、不測の事態が発生した人に対して、その中からまとまったお金を出すという助け合いの仕組みです。
一方で生命保険と共済は、以下のように根拠法令や監督庁などが異なります。
| 生命保険 | 共済 | |
| 運営主体 | 生命保険会社 | 協同組合 |
| 営利・非営利 | 営利目的 | 非営利目的 |
| 加入対象者 | 不特定多数 | 協同組合の組合員とその家族 |
| 根拠となる法律 | 保険業法 | 消費生活協同組合法または農業協同組合法 |
| 監督庁 | 金融庁 | 厚生労働省または農林水産省 |
| セーフティネット | 生命保険契約者保護機構 | なし |
また、生命保険と共済では、以下の通り用語が異なります。
| 生命保険 | 共済 | |
| 契約者(加入者)が支払う金銭 | 保険料 | 掛金 |
| 万一のときに支払われる金銭 | 保険金・給付金 | 共済金 |
| 契約者(加入者)に還元される金銭 | 配当金 | 割戻金 |
ここからは、生命保険と共済の違いを詳しく見ていきましょう。
生命保険とは保険会社が取り扱う金融商品
生命保険は、保険料を支払うことで、被保険者(保険の対象となる人)が亡くなったり、高度障害になったりしたときに保険金が支払われる金融商品です。
生命保険は営利目的の事業
生命保険は、生命保険会社が営利目的で取り扱っている金融商品です。保険会社は、顧客から選んでもらえるように医療環境や法律などを日々研究し、商品の開発や改善に努めています。
生命保険会社は、保険業法をもとに生命保険事業を運営しています。監督庁は、銀行や証券会社などと同じく金融庁です。
なお生命保険には「生命保険契約者保護機構」というセーフティネットがあります。万が一生命保険会社が経営破綻したときは、保険金や年金などが削減される可能性はあるものの保険契約は継続されます。
生命保険の種類
生命保険会社が取り扱っている保険の種類は、以下の通りです。
- 死亡保険(定期保険・終身保険など)
- 個人年金保険
- 学資保険
- 医療保険
- がん保険
- 傷害保険
- 就業不能保険
- 介護保険 など
厳密にいえば生命保険は、1〜3までの保険を指します。生命保険を取り扱えるのは、生命保険会社のみです。
一方で生命保険会社は、火災保険や自動車保険などの損害保険は取り扱えません。4〜8の保険は、第三分野と呼ばれており、生命保険会社と損害保険会社のどちらも取り扱いが可能です。
保険のほとんどは、主契約に特約を組み合わせて保障を選びます。商品のラインナップや選択できる特約、保険金額の上限などは保険会社によって異なります。
基本的に誰でも申し込める
生命保険は、不特定多数の人に向けて販売されているため、年齢などの条件に該当するのであれば基本的に誰でも申し込み可能です。
ただし生命保険の多くは、申込時に健康状態や過去一定期間の傷病歴を告知して、保険会社の診査を受ける必要があります。診査の結果によっては、生命保険に加入できなかったり、「保険金の削減」や「保険料の割増」などの条件が付いたりすることがあります。
共済とは協同組合が提供する制度
共済とは、組合員がお金を出しあって、困った人を助け合うための事業であり、「協同組合」と呼ばれる団体が運営しています。
共済は非営利の事業
共済は、組合員同士の助け合い・相互扶助を目的に運営されている事業であり、営利を目的としていません。
決算の結果、組合員から集めた掛金が余ったときは、契約者に割戻金として戻されます。
共済の種類
代表的な共済とそれを運営する協同組合は、以下の通りです。
- こくみん共済 coop:全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
- 都道府県民共済:都道府県民共済グループ(全国生活協同組合連合会)
- CO・OP共済:日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)
- JA共済:全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
こくみん共済 coop と都道府県民共済、CO・OP共済については、消費生活協同組合法(生協法)にもとづいて運営されています。監督庁は、厚生労働省です。JA共済のみ、農業協同組合法にもとづいて共済事業が運営されています。監督庁は、農林水産省です。
共済では、死亡や病気・ケガでの入院または手術などに対する保障が一通りそろっています。また共済によっては、複数の保障がパッケージされたものも取り扱われています。
なお、ひとつの協同組合が生命保険分野(生命共済)と、損害保険分野(火災共済、自動車共済など)を同時に提供できる点も共済の特徴です。
共済に加入できるのは組合員のみ
共済は、協同組合の組合員にならなければ共済には加入できません。組合員になるためには、所定の条件を満たしたうえで出資金を支払います。
例えば都道府県民共済は、住んでいる場所や勤務先がある場所にある共済に200円の出資金を支払うと組合員になれます。※2022年1月現在、鳥取県と沖縄県では事業が行われていません。
JA共済に加入できるのは、農業の仕事をしている人とその家族です。ただし農業の仕事をしていなくても、JAの協同組合運動に賛同し出資金を支払って准組合員になることでJA共済に加入できます。
生命保険のメリットとデメリット

ここからは、生命保険と共済それぞれを選ぶメリットとデメリットを解説します。
生命保険のメリット
生命保険の主なメリットは、次の通りです。
- 選択肢が豊富
- 保障をカスタマイズしやすい
金融庁から免許を取得して営業している生命保険会社の数は、令和3年12月1日現在で42社です。
※出典:金融庁
それぞれの保険会社が生命保険や医療保険、がん保険などを取り扱っているため、選択肢は豊富といえます。また、外貨建て保険や変額保険など、万一に備えながら資産形成が可能な保険も取り扱われています。
- 外貨建て保険:契約者が支払った保険料を保険会社がドルやユーロなどに両替して運用する保険
- 変額保険:契約者が支払った保険料の一部を、株式や投資信託などで構成された「特別勘定」で運用する保険
また保険会社が定める範囲内で、保険金額や給付金額、付帯する特約などを自由に設定できるため、自分自身に合わせて保障をカスタマイズしやすいです。
生命保険のデメリット
生命保険のデメリットは、主に以下の2点です。
- 保険料が割高
- 知識がなければ選ぶのが困難
生命保険は、営利目的で取り扱われている金融商品であるため、保険料が割高な傾向にあります。また基本的に加入時の年齢や性別に応じて保険料が算出される仕組みであり、高齢になるほど保険料も高くなっていきます。10年などの一定期間で保険契約を更新するたびに、保険料負担が増えていくものもあるのです。
また生命保険に加入するときは、膨大な選択肢のなかから商品や保障を選ばなければなりません。保険や金融、社会保障制度の知識が求められるため、インターネットや書籍などで調べたり、保険のプロに相談したりしなければ、自分自身にあったものを選ぶのは難しいでしょう。
共済のメリットとデメリット

次に、共済のメリットとデメリットをみていきましょう。
共済のメリット
共済の主なメリットは、以下の通りです。
- 掛金が比較的割安
- 年齢や性別にかかわらず掛金が一律のものがある
共済によっては、1,000〜2,000円程度の割安な掛金で、亡くなったときや病気・けが、交通事故による後遺障害などに幅広く備えられます。また共済には割戻金があり、掛金の30%以上が戻ってくることもあるため、実質の負担はさらに低くなるのです。
共済のなかには、18〜59歳(60歳)まで性別を問わず掛金が一律のものがあります。生命保険は、加入時の年齢が高いほど保険料も高くなっていきます。しかし掛金が一律の共済であれば、40代や50代の人も20代の人と同額の掛金で同じ保障に加入が可能です。
共済のデメリット
共済のデメリットは、次の通りです。
- 保障額の上限が低い傾向にある
- 貯蓄タイプの選択肢が少ない
共済の死亡保障額は、最高2,000万〜3,000万円ほどです。5,000万円以上の死亡保障に加入できるものも多い生命保険と比較して、死亡保障額の上限は低いといえるでしょう。 また共済によっては、年齢が65歳以上になると保障額の上限がさらに低くなることがあります。
貯蓄タイプの選択肢があまり多くないのも、共済のデメリットです。なかには、貯蓄性タイプをまったく扱っていない協同組合もあります。さらには生命保険のように、外貨建て保険や変額保険は選べません。
生命保険と共済のどちらを選ぶ?

では、生命保険と共済はそれぞれどのような人に適しているのでしょうか。ここでは、生命保険と共済が向いている人の例を、それぞれ解説します。
生命保険が向いている人の例
生命保険が向いている人の特徴の例は、以下の通りです。
- 手厚い保障に加入したい人
- より自分に合った保障を選びたい人 など
生命保険では、3,000万円を超える死亡保障に加入できます。小さな子どもがいる家庭を経済的に支えている人など、手厚い死亡保障に加入したい方は、保障額の上限が高い傾向にある生命保険に加入すると良いでしょう。
また自分自身にあった保障を選びたい人や、保険金額や給付金額を細かく調整したい人は、選択肢が豊富な生命保険のほうが向いていると考えられます。例えば、亡くなったあとに残された家族が必要な生活費や子どもの教育費などをもとに、死亡保険金額を決めたい方は生命保険を選ぶと良いでしょう。
共済が向いている人の例
共済に向いている人の例は、以下の通りです。
- 金銭的な負担を抑えて保障を準備したい人
- すでに加入している保険の上乗せ保障を準備したい人 など
複数の保障がパッケージされた共済を選ぶと、手頃な掛金で病気やケガ、死亡に幅広く備えられます。例えば、教育費や住宅ローンの返済負担などが家計の支出の多くを占めている人は、共済に加入して備えるのも方法です。
また、すでに生命保険や医療保険などに加入している人は、共済に追加で加入して保障を手厚くしたり不足している保障を補ったりできます。例えば、子どもが独立するまで死亡保障を手厚くし、入院時の保障にも加入したいのであれば、死亡保障や病気・ケガの保障がパッケージされた共済の加入を検討すると良いでしょう。
まとめ

生命保険は、生命保険会社が営利目的で取り扱う金融商品です。一方で共済は、協同組合の組合員が相互に助け合うための事業であり、営利を目的としていません。
生命保険は、数多くの生命保険会社が取り扱っており商品の種類も豊富です。また自分自身の希望や状況に応じて、保障をカスタマイズしやすいです。
共済は、割安な掛金で病気やケガ、死亡などに幅広く備えられる可能性があります。59歳や60歳までは掛金が一定であるものもあるため、手頃な掛金負担で万一に備えたい方は共済を選ぶと良いでしょう。
保険コンパスなら、何度でも相談無料です!

宮里 恵
(M・Mプランニング)
保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。