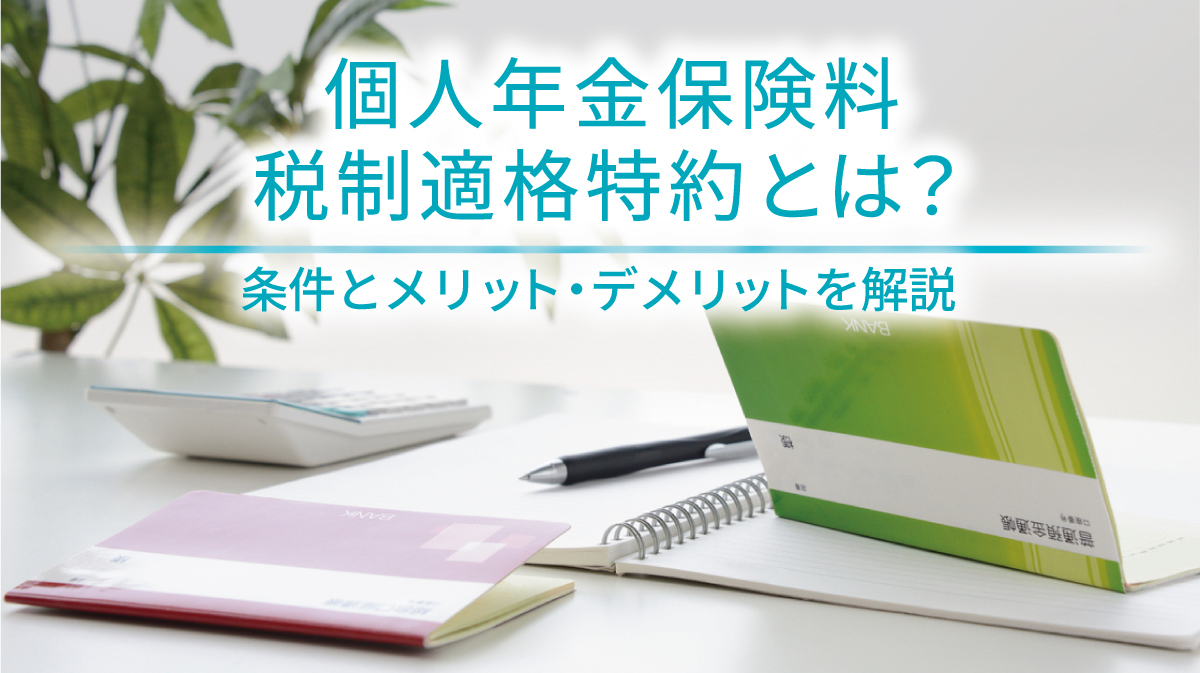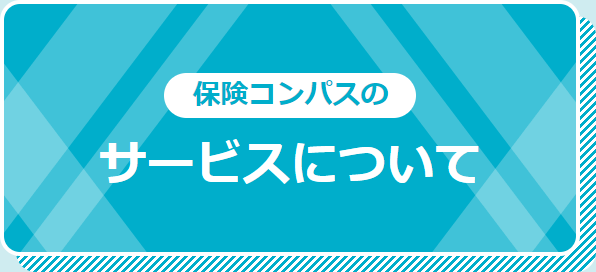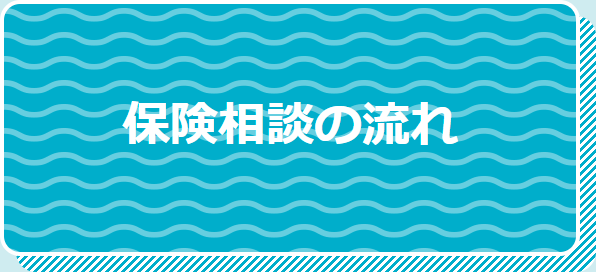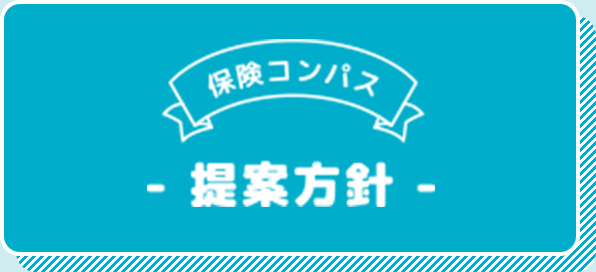実は、すべての個人年金保険で個人年金保険料税制適格特約を付けられるわけではありません。
本記事では、個人年金保険料税制適格特約の概要と特約を付ける条件、メリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。
個人年金保険料税制適格特約とは

保険会社が販売している「個人年金保険」には、「個人年金保険料税制適格特約」という特約を付けることができます。
特約を付ければ、生命保険料控除の一つである「個人年金保険料控除」を受けられます。より簡単に言えば、控除枠を増やして節税効果を高くできる特約が個人年金保険料税制適格特約です。
ただし、この特約は誰でも付けられるわけではありません。
ここでは特約を付ける条件、すでに契約している人が途中で特約を追加する方法について解説していきます。
個人年金保険料税制適格特約の条件
同じ個人年金保険でも、契約の方法によっては個人年金保険料税制適格特約を付けられません。
特約を付ける条件は、以下のとおりです。
- 年金の受取人は被保険者と同一であること
- 年金の受取人は保険料を実質的に支払っている人(一般的には契約者)または配偶者になっていること
- 保険料の支払い期間が10年以上で、定期的に支払う契約であること
- 確定年金や有期年金の場合は、年金の受取開始は60歳以降、かつ年金受取期間が10年以上であること
なお対象となる「個人年金保険」には、いわゆる変額保険は含まれません。変額保険は一般の生命保険料控除の対象になります。
途中付加できる可能性も
契約当初は特約を付けていなくても、後から契約内容を変更すれば特約を途中で付加できる可能性があります。
契約内容の変更によって個人年金保険料税制適格特約の条件に該当すれば、保険会社によっては特約を途中付加できるかもしれません。
保険会社によって対応は異なります。詳しい対応については、現在契約中の保険会社に確認しましょう。
個人年金保険料税制適格特約のメリット

個人年金保険料税制適格特約のメリットは以下の2つです。
- 節税効果を高められる
- 無料で付加できる
節税効果を高められる可能性がある
一番のメリットは節税効果です。
現在、保険に関する所得控除には以下3つの控除枠があります。
| 控除枠の種類 | 内容 |
| 一般の生命保険料控除 | 終身保険、定期保険といった生命保険、学資保険などを契約すると受けられる控除枠 |
| 介護医療保険料控除 | がん保険、医療保険、介護保障保険などを契約すると受けられる控除枠 |
| 個人年金保険料控除 | 「個人年金保険料税制適格特約」を付けた個人年金保険を契約すると受けられる控除枠 |
上記の控除枠にはそれぞれ最高4万円の所得控除が設定されています。
すでに生命保険を契約していて「生命保険料控除枠」を限度額いっぱい使っていても、別枠で「個人年金保険料控除枠」を使えば控除の合計金額が増えます。控除額が増えればそのぶん税金の対象になる所得が減るため、所得税・住民税の軽減につながります。
したがって個人年金保険料税制適格特約は、節税効果を高める可能性がある特約なのです。ただし、節税効果があるかどうかは契約者の納税額や保険契約状況によって異なります。誰でも絶対に税金を軽減できるわけではありません。
無料で付加できる
「特約」というと、保険料がその分上がるイメージがあるかもしれません。
しかし個人年金保険料税制適格特約は、条件さえ満たせば誰でも無料で契約に付加できます。
すでに契約している個人年金保険に途中で特約を付ける場合でも、手数料が発生することはありません。条件さえあれば無料で保険料控除の枠を増やせるのがメリットです。
個人年金保険料税制適格特約のデメリット

一方で、個人年金保険料税制適格特約には以下のようなデメリットもあります。
- 契約内容が制限される
- 誰でも節税できるわけではない
契約内容に縛りが出てしまう
特約を付けるためには、先述した「個人年金保険料税制適格特約の条件」をすべて満たす契約内容にしなければなりません。
保険料の払い込み期間は10年以上が条件のため、一括払いで支払う「一時払い契約」は対象外です。また、年金受取開始年齢も60歳以降でなければなりません。早期退職して早めに年金を受取るなど、ライフプランの状況にあわせた対応がしづらい点はデメリットと言えます。
節税効果を優先して特約を付加するか、ライフプランや資金状況にあわせた保険契約を優先して特約を外すか。契約の方法に正解はないため、各家庭で適した方法を選ぶことが大切です。
全員に節税効果があるわけではない
個人年金保険料税制適格特約は節税効果が高まる人は限定されているため、誰でもメリットがあるわけではありません。
<節税の可能性がある人>
- すでに「一般の生命保険料控除」の枠を上限額まで使い切っている
- まだ「個人年金保険料控除」の枠を使っていない
- 軽減できる税金(所得税・住民税)を支払っている
<節税の可能性が低い・効果を得にくい人>
- 「一般の生命保険料控除」の枠を使っていない、枠が余っている
- 軽減対象になる税金(所得税・住民税)を支払っていない
一般の生命保険料控除枠を使っていない人とは、生命保険や学資保険などの保険契約がないケースです。元々契約がなく控除枠が余っている場合は、個人年金保険料税制適格特約を付ける効果は薄いでしょう。
なぜなら、特約で付けなくても一般の生命保険料控除枠を活用できるため、付けても付けなくても控除額は同じだからです。
また専業主婦や扶養内パートなど、配偶者の扶養に入っていて納税していない人も同様です。納税義務がなければ、控除額が増えても減っても税金がかかることはありません。個人年金保険料税制適格特約は、あくまで控除枠を増やすためのものなのです。
自身の納税額や既存の保険契約・保険料控除枠の活用状況を見たうえで、特約を付けるメリットがあるかどうか、よく考えるようにしましょう。
生命保険料控除をフル活用するポイント

個人年金保険料税制適格特約のメリットを得るには、生命保険料控除の仕組みを理解して各控除枠をフル活用する必要があります。
ここで改めて3つの控除枠を見てみましょう。
| 控除枠の種類 | 対象となる保険 | 控除限度額 |
| 一般の生命保険料控除 | 生命保険(終身保険、定期保険、養老保険)、学資保険、変額保険、「個人年金保険料税制適格特約」を付けていない個人年金保険 | 所得税:4万円 住民税:2.8万円 |
| 介護医療保険料控除 | がん保険、医療保険、介護保障保険など | 所得税:4万円 住民税:2.8万円 |
| 個人年金保険料控除 | 「個人年金保険料税制適格特約」を付けた個人年金保険 | 所得税:4万円 住民税:2.8万円 |
上記の控除額を活かすポイントは、以下の2つです。
- 契約している保険が該当する控除枠は何になるか確認する
- 世帯内で納税額の高い人が保険料を支払う
まずは、契約中の保険がどの控除枠になるかを確認しましょう。
すでに終身保険や学資保険を複数契約していて控除限度額を使い切っている場合は、個人年金保険料税制適格特約を付加して個人年金保険料控除を新たに使うチャンスです。
また、夫婦のどちらかに控除を集中させている場合は、それぞれ控除を分散して保険料を使うことが可能です。なぜなら生命保険料控除を受けられるのは契約者ではなく、実質的に保険料を払っている人だからです。
たとえ妻の保険契約でも、保険料を支払っているのが夫ということが明らかであれば、夫が保険料控除を受けられる可能性があります。保険料控除を受けて節税効果があるのは、納税している人だけです。
したがって扶養内で働いている人や、専業主婦の人は納税額がないため、保険料控除を受ける意味がありません。その場合は保険料を払っている夫が妻の加入している保険の保険料控除を受けることができます。
各家庭の実態にあわせて、控除対象者を適切にすることも大切です。
まとめ

「個人年金保険料税制適格特約」は、一定の条件を満たした個人年金保険の契約で付けられる特約です。特約を使えば個人年金保険料控除枠を使えるため、節税効果を高められる可能性があります。
ただし、個人年金保険料税制適格特約を使えばすべての人の税金が軽減されるわけではありません。現在の保険契約や納税の状況によって、得られるメリットは変わってくるでしょう。
まずは保険契約の内容を確認し、家庭内で納税額の高い人がまんべんなく控除枠を使えるように調整することが大切です。確認方法がわからない人は、保険代理店や保険会社の担当者に確認し、あわせて控除の活用方法を聞いてみてください。
保険コンパスなら、何度でも相談無料です!

宮里 恵
(M・Mプランニング)
保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。