夫婦の老後資金を考えるときに欠かせないポイントは、持ち家の有無です。
持ち家があるかないかで、老後にかかるお金は変わってきます。この記事では、夫婦の老後の必要額を計算する方法から、持ち家の有無で異なる老後資金の考え方、老後資金の備え方まで、わかりやすい解説します。
持ち家の活用方法も含めて、夫婦の老後資金について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
夫婦の老後資金はいくら必要?生活費の平均は月22.4万円だけど……

まずは、夫婦の老後資金の平均像を見ていきましょう。
総務省の家計調査によれば、65歳以上で夫婦のみの無職世帯の生活費は、月22万4,390円となっています。
65歳以上・夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の毎月の家計
- 可処分所得(公的年金を主軸とした手取り収入):22万5,501円
- 消費支出(住居費や食費などの生活費):22万4,390円
※収入から差し引かれる非消費支出(社会保険料や税金など)は上記に含めていません
出典:総務省 家計調査より「図2 65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)及び65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支 -2020年-」
老後働かず年金暮らしの夫婦の平均的な生活費は、毎月約22.5万円です。この金額はさまざまな媒体で「老後資金の平均的な生活費の目安」として紹介されているため、見たことがある人もいるのではないでしょうか。
しかし、家計調査の内訳で住居費を見ていくと、1万4,518円という安さに驚きます。平均的な住居費がここまで安い理由は、持ち家があり住宅ローンを完済している夫婦が平均を引き下げているからです。
ただ、老後は賃貸物件に住む夫婦や、老後も住宅ローン返済が続く夫婦もあるでしょう。平均データを自分の家庭に照らし合わせると、どうしても収支のギャップが出てきます。
特に住居費は各家庭で大きな違いが出る部分なので、夫婦の持ち家の状況にあわせて調整しつつ、各家庭にとって必要な老後資金を考えることが大切です。
老後に必要な金額を把握する方法

ここでは、老後に必要な金額の目安を簡単に把握する方法を解説します。
持ち家の有無による調整は後でしますが、まずは以下の方法で夫婦の老後資金を計算してみてください。
- 毎月の収入を計算する
- 毎月の支出を計算する
- 複数の可能性をシミュレーションする
それぞれの方法について、詳しく解説していきます。
1.毎月の収入を計算する
老後生活の柱となる収入がいくら見込めるのかを計算します。
老後に見込める主な収入は、以下の4つです。
| 公的年金 | 公的年金制度の老齢給付の金額 |
|---|---|
| 私的年金 | ・公的年金の上乗せを目的として自助努力で用意する年金 ・自ら加入する国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)、民間保険会社の個人年金保険などがある |
| 退職金 | ・各企業が導入する退職金 ・確定給付企業年金(DB)や確定拠出年金(DC)制度などがある |
| 労働収入 | ・老後に働いて得る収入の見込み ・会社員で65歳以降は継続雇用制度を利用する人は、その見込み収入 |
公的年金の受給見込額は、毎年誕生月前後に届く「ねんきん定期便」や、事前登録で年金額を試算できる「ねんきんネット」で確認できます。私的年金は自身の利用している制度の団体に確認し、退職金は勤め先に確認しましょう。
上記のうち、労働収入は現時点で試算が難しい収入です。フリーランスで定年がない場合も会社員で継続雇用制度を利用する場合も、老後も継続して働くには一定の体力維持が前提条件となります。
老後の労働環境がどうなっているかはまだわからないため、万が一働けない可能性も加味したうえで計算しましょう。
2.毎月の支出を計算する
老後、毎月発生する支出額を計算します。支出額は大きく分けて以下の2つです。
| 消費支出 | 日常の生活をするにあたり、必要な商品やサービスを購入して支払う金額 ※いわゆる生活費のこと |
|---|---|
| 非消費支出 | 社会保険料や各種税金など ※消費を目的とせず、原則として世帯の自由にならない支出 |
非消費支出の金額は、老後の労働環境、収入、自動車や住宅の保有状況によって変化しますが、一般的には収入のうち20%程度が非消費支出と覚えておきましょう。
一方、老後資金の計算に大きく関係するのが消費支出=生活費です。老後の生活をイメージしながら、毎月いくらぐらいあれば生活できるか計算してみます。
老後の生活費
- 住居費
- 食費
- 水道・光熱費
- 日用品
- 電話代を含む通信費
- 医療費
- 交通費
- 趣味・娯楽費
- 交際費
- その他雑費
先述した総務省の家計調査によると、高齢夫婦の家計でもっとも支出が多い費目は食費でした。老後は自宅で3食食べることになり、現役時代と比べて時間があるからこそ食費が高くなる可能性もあります。現在の生活費と比べながら、老後の生活費の目安を計算してみてください。
また、生活費を考える際は、冠婚葬祭などで発生する臨時費用を一定数計上しておきましょう。老後は子どもの結婚や出産、友人・知人の葬式などで、慶弔費が発生する可能性が高くなります。余裕をもって生活費を見積もっておくことが大切です。
3.複数の可能性をシミュレーションする
これまで計算してきた1の「老後の収入」から2の「老後の支出」を差し引くと、老後の家計において毎月どの程度の不足額が発生するのかを確認できます。
ただ、老後の収入も支出も現時点では机上の計算に過ぎません。いつまで働けるのかによっても金額は変わってくるため、複数の可能性を加味してシミュレーションを作っておくといいでしょう。
キャッシュフロー表を作り、老後のお金の流れを可視化しておくことも大切です。
夫婦の老後資金は持ち家の有無で大きく違う

前項の「老後に必要な金額を把握する方法」で簡単な老後資金を計算したら、持ち家の有無に応じて老後資金を調整していきます。
夫婦の老後資金の必要額は、持ち家の有無によって大きく違います。ただ、持ち家があると有利になるわけではありません。たとえ持ち家があっても、以下の夫婦は賃貸派の夫婦より支出が増える可能性があるので気をつけましょう。
- 老後(定年後)も住宅ローン返済が続く予定
- 退職金で住宅ローンを一括返済する予定
- 自宅の固定資産税が高い
- 築年数の経過に応じて大規模修繕が発生。修繕積立金が高額になる(マンション住まいの場合)
個々の状況によってもかかる費用は変わってくるため、持ち家があるから住居費を抑えられるとも言えないのです。
ここでは、持ち家ありの人となしの人がそれぞれ老後資金を考えるうえで気をつけるポイントを解説します。
【持ち家あり夫婦】老後資金を考えるときに気をつけたいポイント
持ち家ありの夫婦が老後資金を考える際、特に気をつけたいポイントは以下の2つです。
- 住宅ローンを老後までに完済できるよう返済計画を立てる
- 老後の住宅の維持・メンテナンス費を見積もりしておく
住宅ローンの返済状況は、老後の生活に大きく影響します。老後もローン返済が続けば支出は増えますし、退職金で一括返済すれば老後の収入が減ることになります。退職金は老後資金の貴重な原資です。
まとまった退職金を運用に回せばさらに老後収入を増やせる可能性もあるため、住宅ローンの一括返済に退職金を使うのはおすすめしません。老後までに繰り上げ返済をこまめにしてローンを完済し、退職金には手をつけないようにしましょう。
維持・メンテナンス費は、持ち家ならではの費用です。
持ち家がある以上、毎年固定資産税はかかりますし、古くなった自宅を修繕するための費用も必要です。マンションの場合は、築年数が35年以上だと大規模修繕が必要になり、管理費や修繕費が高額になる可能性があります。
住宅ローンを完済しても、現在と同額の管理費・修繕積立金で住めるわけではないのです。
一方、戸建ては各種設備の寿命が10年〜20年程度と言われています。老後も自宅に住み続ける場合は、外壁の塗装や屋根の張り替え、水道管の取り替え、その他水回りのリフォームなどが必要になってきます。
必要な箇所ごとに見積もりを出し、メンテナンス費用の目安をつけておきましょう。
【持ち家なし夫婦】老後資金を考えるときに気をつけたいポイント
一方、持ち家はなく老後は賃貸生活という夫婦の場合には、以下のポイントに気をつける必要があります。
- 老後の生活費には賃貸費用を含めて考えておく
- 配偶者が亡くなったときの住居を考えておく
賃貸費用は、多めに見積もって老後の生活費に含めておきましょう。一般的な老後資金の生活費は【持ち家あり・住宅ローン完済】が前提になっていることが多いです。賃貸の場合は固定資産税や住宅のメンテナンス費がかかりませんが、その分家賃や引っ越し代、駐車場代などが持ち家よりも多くかかりがちです。
また、配偶者が亡くなったときの住居を考えておくことも大切です。配偶者が亡くなったことを機に一人暮らし用の賃貸に引っ越そうと思っていても、高齢を理由に入居を断られる可能性もあるからです。
今の住居に住み続けるとしても、夫婦で払ってきた家賃を1人で支払わねばならず、家計が苦しくなることもあるでしょう。
高齢の一人暮らしにはこのような問題があるため、配偶者が亡くなった後の住居も考えると、老後はあらかじめ単身世帯でも暮らせる賃貸物件を見つけておくのも方法です。
資金に余裕がある場合は施設に入ることも念頭に入れ、シミュレーションしておくと安心でしょう。
夫婦の老後資金を備える方法

老後資金の目安がついたら、次は老後資金の備え方を見ていきましょう。
「老後資金の必要額はわかったけど、今からどうやって備えていけばいいの?」と悩んでいる人は、以下3つの方法を参考に今から準備を始めてください。
- 老後も長く働ける環境・体力作り
- iDeCoや小規模企業共済で節税しながら老後資金を準備
- 持ち家がある場合は資産として活用することも検討
それぞれを詳しく見ていきましょう。
1.老後も長く働ける環境・体力作りをしておく
老後資金の不足を手っ取り早く解消する方法は、働くことです。
ただ、老後も長く働けるためには働ける環境と体力作りが欠かせません。長く働くための土台を今から作っておくことが大切です。
幸い、社会全体の高齢化が深刻な日本では、高齢者の就労が促進されています。会社員であれば60歳の定年退職後も継続雇用制度で65歳まで働けることが多いですし、70歳までの継続雇用制度を導入する企業も出てきました。
今の現役世代が65歳になる頃には、高齢化就労の流れはより活発になっていくでしょう。
ただ、継続雇用制度を利用すると現役時代よりも収入が大幅に下がることがあります。そもそも、体力がなければ長く働けません。
老後は自分のペースで働ける事業を起業する方法もあります。さまざまな可能性を模索しながら、今のうちに老後も快適に働ける環境と体力作りに励みましょう。
2.iDeCoや小規模企業共済で節税しながら老後資金を準備する
今から老後資金を備える方法として、おすすめの資産形成方法はiDeCoと小規模企業共済です。なぜなら、この2つは積み立てた金額=掛金を全額所得控除でき、節税効果が非常に高いからです。
老後資金を備えるおすすめの資産運用方法
- 会社員、自営業者向け:iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 自営業者向け:小規模企業共済
iDeCoとは、個人の采配で掛金を運用して将来の私的年金を作る制度です。毎月の掛金は全額が所得控除の対象となります。
原則として60歳まで引き出しができず、毎月一定の手数料がかかります。運用方法は定期預金か保険商品、投資信託があり、投資信託を選べば運用で将来の年金額が変動します。「多少手数料がかかってもいいので、強制的かつ積極的に運用したい」人に向いています。
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者向けの退職金制度です。受け取れる共済金の金額は、掛金納付月数に応じて80%~120%相当額となっています。短期間で解約すれば元本割れになる可能性がありますが、貸付制度があるためiDeCoよりは続けやすいです。
「リスクを抑えて安定運用し、事業廃業時の退職金を自分で備えたい」という自営業者に向いています。
なお、自営業者はiDeCoと小規模企業共済を併用可能です。
3.持ち家がある場合は資産として活用する
持ち家ありのご夫婦は、持ち家を一つの資産として活用することも考えておきましょう。
子どもたちが独立した後は家が広すぎて、維持が大変という場合もあるでしょう。また、子どもが遠方に住んでいて、持ち家の生前贈与・相続を拒否される可能性もあります。
老後は持ち家に住み続けることにこだわりすぎず、以下の方法も今から検討してみてください。
- 持ち家を売却し、老後は施設や賃貸物件に住む
- 持ち家を賃貸にして賃貸収入を得る
- 子どもと話し合い、建て替えして二世帯住宅にする
- 持ち家を担保に資金を借りるリバースモーゲージを検討する
持ち家は立派な資産です。今と同じ形で住むことにこだわらず、さまざまな活用方法を検討しておきましょう。
まとめ
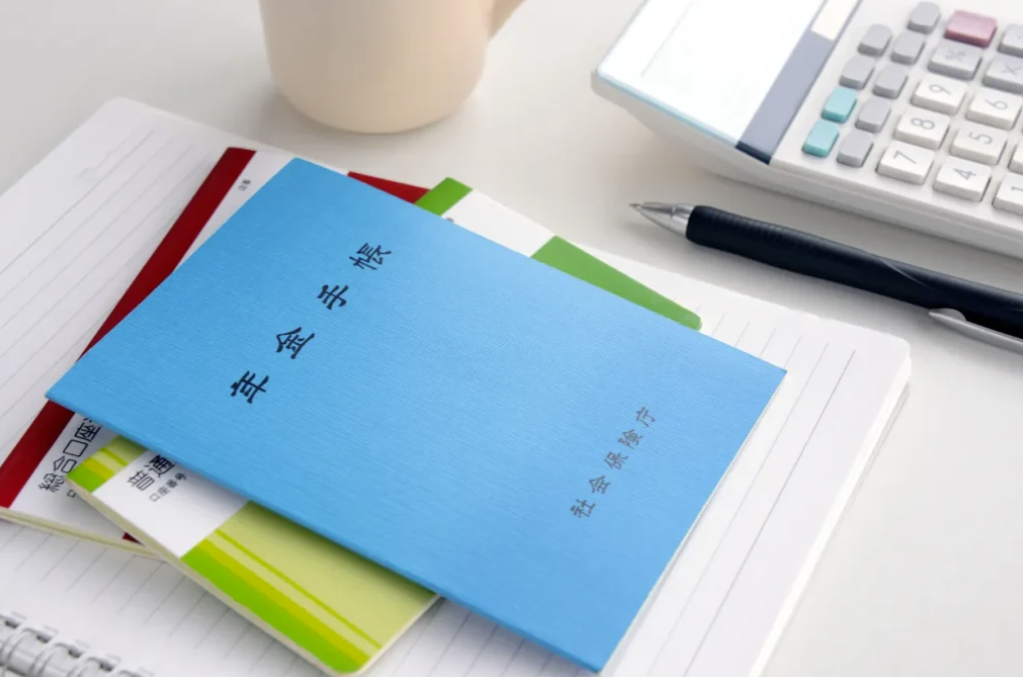
夫婦の老後資金を考える際は、以下のステップで老後に向けた準備を始めてください。
<老後資金を備える具体的なステップ>
- 老後資金の目安を算出する
→老後の収入と支出を計算し、複数のシミュレーションを元に必要額を算出する - 老後の持ち家の有無に応じて、必要額を調整する
- 老後資金の準備
→老後も長く働くための環境・体力作り/節税しながら資産形成/持ち家を資産として活用
持ち家ありの夫婦は、老後までに住宅ローンを完済する計画を立てておきましょう。一方、持ち家がない夫婦は配偶者が亡くなった後の住居を具体的に考えておいてください。持ち家の有無によって気をつけるポイントが異なるため、この記事を参考に今からできることを始めてみてくださいね。
保険コンパスなら、何度でも相談無料です!

宮里 恵
(M・Mプランニング)
保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。



